|
(記 2025/8/-)
|
|
|
|
(記 2025/8/-)
|
|
鎌倉の深沢、上町屋 付近は「古道鎌倉道上の道」(の一部)が通っていました。
新田義貞の鎌倉攻め(元弘3年(1333))のおりには激戦「洲崎合戦」の地となりました。その場所は洲崎古戦場といわれています。 |
| もどる | すすむ | 鎌倉と鎌倉郡の歴史 indexへ |
| << アプローチ >> |
|
最寄り駅は、湘南モノレールの「湘南深沢」駅; または「湘南町屋」駅です。湘南モノレールはJR大船駅と湘南江ノ島駅を結ぶ路線です。
|
|
こちらで紹介した寺社や史跡等は、これらの駅から歩いて容易にまわれる範囲にあります。
(付近の略地図 は ) 深沢 (手広 ・ 笛田 ・ 梶原 ・ 寺分 ・ 常盤) 方面 コース見どころ 周辺 略地図 のページへ |
| 洲崎古戦場(すざきこせんじょう) 鎌倉 |
|
|
湘南モノレールの湘南町屋駅から目の前の道路を深沢方面に向かいます。道路沿いには湘南モノレールの軌道が設置されています。わずかに進むと右手に入る路地の角隅に「洲崎古戦場」の史跡碑が建っています。
この辺りが、新田義貞の鎌倉攻め(鎌倉幕府滅亡のとき)(元弘3年(1333))のおりの、激戦「洲崎合戦」の地と思われます。 深沢方面に展開する新田軍に数十万対し幕府軍(北条方)の精鋭6万が突撃を繰り返し壊滅したといいます。 「洲崎合戦」について、推測を含め後記します。 |
|
|

|
|

|
|

|
|
| 「洲崎古戦場」の史跡碑付近から深沢方面 | 「洲崎古戦場」の史跡碑のある路地 | 「洲崎古戦場」の史跡碑 | ||||
|
洲崎古戦場 |
洲崎古戦場 | 洲崎古戦場 |
| 陣出の泣塔(じんでのなきとう) ; 深沢文和五年銘石造宝篋印塔(市文) 鎌倉 |
|
|
「洲崎古戦場」の史跡碑から深沢方向に進むと道路右側にフェンスに囲まれたJR東日本大船工場跡地の広大な敷地があります(2025/7/- 現在)。この敷地跡地北側のフェンスに沿った右手に分岐する道をたどります。
しばらく行くと、フェンスの内側に樹木の茂ったこんもりとした小山があります。この元に「石造宝篋印塔(文和五年銘)」(市指定有形文化財,(文和五年(1356))(塔高203cm)が建っています。安山岩製、関東形式宝篋印塔の典型と言えるものです。 基壇には、「願主行浄 夜造立 石塔婆 各々檀那 現世安寧 後生善処 文和五年丙申二月廿日 供養了」と刻まれています。 文和五年(1356)は、新田義貞の鎌倉攻め(元弘3年(1333))須崎合戦から23年後なので、そのおりの戦没者の二十三回忌の供養塔であると考えられます。しかし、それを含め由緒など確かなことは不明です。 また、通称「陣出の泣塔」、「泣塔」と呼ばれています。塔が手広の青蓮寺に移されたとき、住職の夢枕に立って元に地に戻りたいと泣いたと云われます。また戦後、撤去しようとすると数多くの死傷者が出たとも云います。そんなことから、「泣塔」と呼ばれ、祟りがあるとされ、移動や取り壊しは禁忌とされています。なお「陣出」とはこの辺りの地名で「洲崎合戦」に由来するとおもわれます。 なお、現在(2025/7/-)は、鎌倉市の深沢地域整備事業(令和6年度〜)のため敷地フェンス内は立ち入りが禁止されており見学することができません。 |
|
|
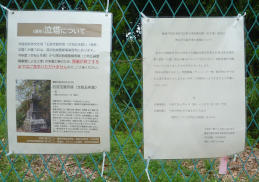
|
|

|
|
| 陣出の泣塔についての説明 | 陣出の泣塔がある小山 | |||
|
|
| 天満宮(てんまんぐう) (上町屋) 鎌倉 上町屋 |
|
|
JR東日本大船工場跡地の北側フェンス沿いの道、「陣出の泣塔」の前をさらに北西方向に進むと、やがて道は右におれ、フェンスから離れるようになります。右に入った処、右手に天満宮(上町屋)が建ちます。
上町屋の鎮守です。 |
|
|

|
|

|
|

|
|
| 天満宮(上町屋) 鳥居から境内 | 天満宮(上町屋) 本殿 | |||||
|
|
天満宮(上町屋) 庚申塔 |
|
|
<<勧請・由緒 等 >>
祭神は菅原道真です。 勧請、由緒に関しては不詳です。社伝によると、上総介平良文(かずさのすけたいらのよしふみ)が霊夢により天神を祀ったのが始まりとのことです。そのことからから、平安中期の創建と思われます。 平良文(たいらのよしふみ)(村岡良文)に関して、以下のページを参照してください。 御霊神社(藤沢村岡、宮前) のページへ <<境内 (庚申塔、石塔 等)>> 正面の石造の鳥居(天保11年(1840)正月、建立)をくぐると、すぐ両脇に狛犬が建ちます。正面に社殿が建ちます。現在の社殿は天明元年(1781)の再建と云います。 社殿のまわりには稲荷社、松尾社などの境内社も建ちます。 社殿の左わきに寛文十年銘庚申塔(市指定有形民俗文化財、寛文10年(1670))が立っています。それに並んで菅原道真と云われるレリーフ像を刻んだ石仏(正徳2年(1712))が立っています。 社殿に向かって手前右側には、富士山講の石塔(元治元年(1864)11月 建立)が立っています。 |
|
|

|
|

|
|

|
|
| 富士山講の石塔 | 狛犬 左側 | 狛犬 右側 | ||||
|
天満宮(上町屋) |
天満宮(上町屋) | 天満宮(上町屋) |
| 泉光院(せんこういん) 天守山高音寺泉光院(てんしゅざんこうおんじせんこういん) 真言宗 |
|
|
天満宮(上町屋)の前の道をそのまま進むと、先に泉光院の敷地に突き当たります。右に正面山門に回り込みます。
創建、由緒等は、火災で寺史等記録が失われたたため不明とのことです。 |
|
|

|
|

|
|

|
|
| 山門 から 境内 | 境内 参道脇宝篋印塔 | 境内 参道脇名号碑 | ||||
|
泉光院 |
泉光院 | 泉光院 |
|
|
<<山門から境内参道、石塔等>>
山門をくぐり境内に入ると参道の先正面に本堂が建っています。参道の途中に左右に立派な石塔が建っています。左は四方に金剛界四仏の種子を刻んだ宝篋印塔(安永8年(1779))、右は名号碑(安政5年(1858))です。 <<本堂、本尊 他持仏 等>> 本堂は、昭和32年(1954)に再建されたコンクリート製の新しいものです。 本尊は、木造阿弥陀三尊立像(阿弥陀如来、観音菩薩、勢至菩薩)です。他に、木造不動明王坐像、木造愛染明王坐像、木造弘法大師坐像を安置しています。 <<薬師堂 地蔵堂 他石仏 等>> 山門をから境内に入った処、左手に薬師堂が建ちます。江戸時代の制作といわれている木造薬師如来坐像が安置されています。 薬師堂の右奥に地蔵堂が建ちます。「いぼとり地蔵尊」と記されて札が掲げられて居ます。 地蔵堂の右側には、数体の石仏、石塔が並んで置かれています。 右側、錫杖(しゃくじょう)を持った十一面観音の浮彫の石仏(文政4年(1821))12月銘。左に馬頭観音を祀った石塔。さらに左に光明真言供養塔(文政4年(1821)8月銘)。さらに左に馬頭観音の浮彫の石仏(享和3年(1803)正月銘)。 さらに奥に六地蔵(貞享元年(1684)建立という)が並んでいます。 |
|
|

|
|

|
|

|
|
| 本堂前 大師像 | お参りのとき、大念珠を回します | 本堂内部 | ||||
|
泉光院 |
泉光院 本堂 | 泉光院 本堂 |
|
|

|
|

|
|

|
|
| 薬師堂 | 地蔵堂「いぼとり地蔵尊」 | 地蔵堂内 石仏 | ||||
|
泉光院 境内 |
泉光院 境内 | 泉光院 境内 |
|
|

|
|

|
|
| 石仏 石塔 | 六地蔵 | |||
|
泉光院 境内 |
泉光院 境内 |
| 洲崎、上町屋に残る鎌倉古道 について |
|
|
洲崎、上町屋の辺りは、中世の古道「古道鎌倉道上の道」(の一部?)が通っていたと思われます。また、「鎌倉古道」と云われる道があります。
泉光院の門前から南東方向へ向かう道が「鎌倉古道」と云われる道です。途中に双体道祖神や石塔の一部らしきものなどが残されています。これらは江戸末期ころのものと思われます。 |
|
|

|
|

|
|

|
|
| 鎌倉古道 JR東日本大船工場跡地方向 | 鎌倉古道 泉光院方向 | 石仏(?) | ||||
|
鎌倉古道(洲崎) |
鎌倉古道(洲崎) | 鎌倉古道(洲崎) |
| 「新田義貞の鎌倉攻め」と「洲崎合戦」 について (推測 等) |
|
|
<<新田義貞(にったよしさだ)の鎌倉攻め>>
元弘3年(1333)5月8日、新田義貞は、幕府を倒すため上野国新田庄(群馬県太田市)に挙兵しました。その数150騎。その日の夕方には越後の同族2千騎、甲斐・信濃の源氏5千騎が加わり、大部隊となりました。 義貞の軍は鎌倉道上の道をひた走り、よく9日の夕暮れには20万騎になり、鎌倉を包囲した18日早朝にはさらにその数倍の大軍になっていたといいます。 18日、義貞は軍を三つに分け、新田方は化粧坂、巨福呂坂、極楽寺坂の3方面から総攻撃を行いました。しかし守りの強固な切通(きりどおし)を破ることは出来ず総攻撃は失敗に終わりました。 その後、22日未明、新田方の極楽寺方面軍により稲村ヶ崎の防衛線が突破され、新田方は鎌倉に乱入、そして北条氏総領の北条高時(ほうじょうたかとき;鎌倉幕府14代執権)以下一族は自害し、鎌倉幕府は滅亡しました。 <<「洲崎合戦」の経緯>> 18日の新田方の総攻撃は、未明もしくは前日に各方面軍(化粧坂、巨福呂坂、極楽寺坂の3方面軍)が移動を開始し始まりました。新田軍が集結し3軍の編成をし総攻撃の準備をした場所は、深沢付近でしょう。 一方の、幕府方に動きがありました。18日、赤橋(北条)守時が率いる精鋭6万騎が小袋坂(巨福呂坂)から出撃、山崎を経て深沢に向かいました。そして洲崎にて数十万の新田軍に対峙しました。そして、一日一夜に65度打って出て、やがて守時に従う数は300騎あまりになり、部隊は壊滅しました。守時と配下90余は自刃をし果てたと云います。 <<「洲崎合戦」を考察する(推測)>> 「洲崎合戦」は北条方が仕掛けた戦いです。その結果、北条方は精鋭6万騎を失い、多大な損害を出しました。何故、北条方はこのような無謀と思える戦いを仕掛けたのか疑問が残ります。 北条方の部隊は精鋭の騎馬からなっていました。これは防衛戦には向きません。機動力を活かした攻撃や陽動などに向いている部隊です。そのことからも、推測として、 ・新田軍の側面を突き混乱を誘う。・側面を突破し後方に回り込む。・さらに切通の防衛部隊と連携し挟撃を計る。・陽動や後方撹乱を計る。などを画策してと思われます。 そうだとして、タイミングとして新田方が3方面軍の編成などでゴタゴタしている時でしたら、成功の確率は幾分高かったかもしれません。しかしそれでも難しかったでしょう。実際には、合戦が始まったときは、新田方の3軍の編成は終わり、新田方の左翼、堀口貞満、大島守之が率いる巨福呂坂方面軍が洲崎・山崎方向に移動を開始した頃です。北条方赤橋隊はそれと正面で激突することになりました。初期の突撃で無謀な戦いであることは感じ得たはずです。早々に、撤退し戦力の温存を計るべきであったでしょう。 それをしなかったのは、北条方の指揮系統中枢が混乱したためかと思われます。 なお「新田義貞の鎌倉攻め」「稲村ヶ崎の戦い」については以下のページも参照してください。 稲村ヶ崎・稲村ヶ崎古戦場 のページへ |
| もどる | すすむ | 鎌倉と鎌倉郡の歴史 indexへ | このページの 上へ |